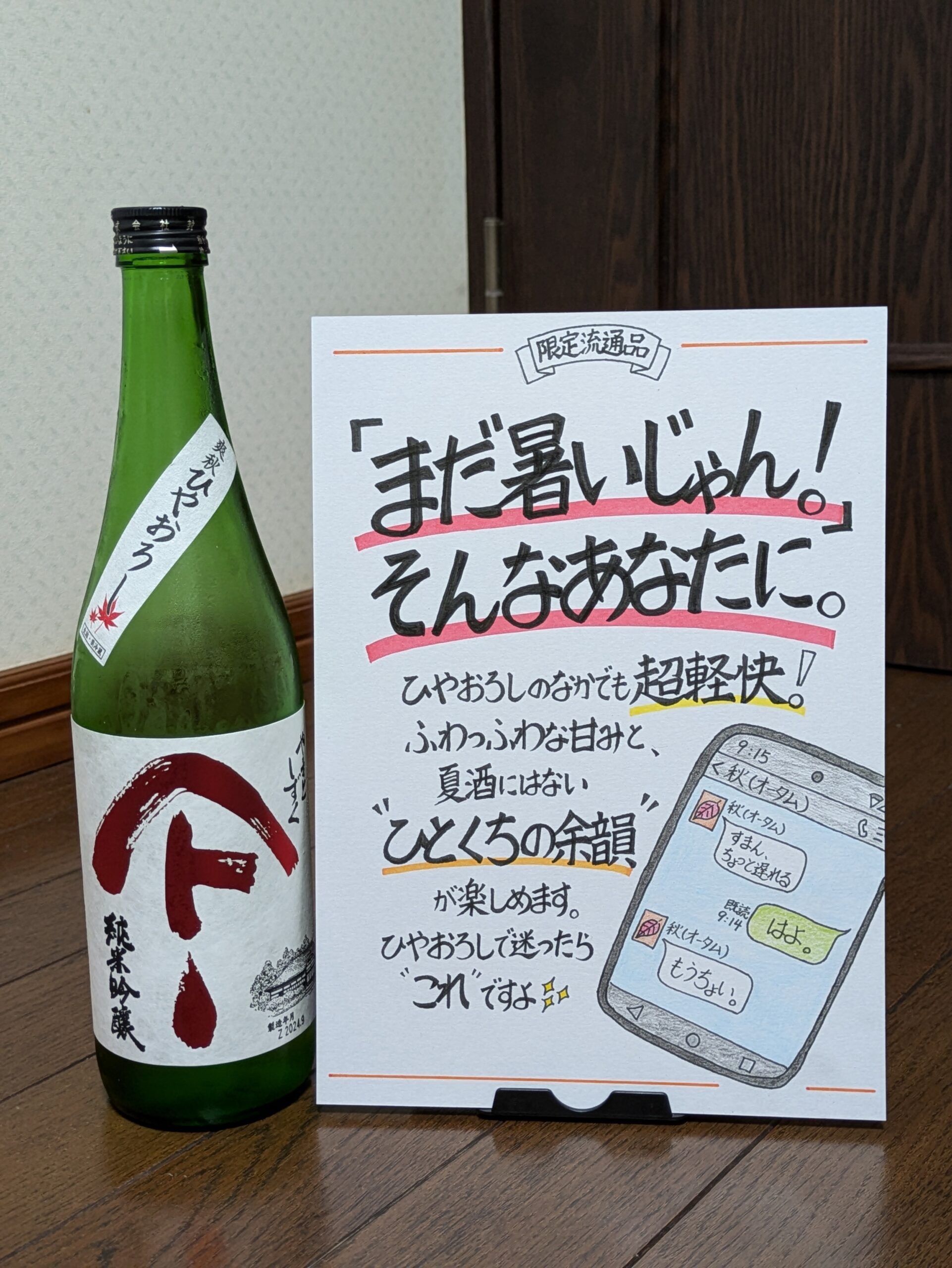こんばんは、いしかわです。
個人的にはこう思っています。
『やまとしずくにハズレなし』
どれを飲んでもおいしいし、どれが発売されても欲しいと思う。
買いたい飲みたい、あれば頼みたい。そんなブランドです。
なのでこの1本……
オススメですよ。
それでは今回はこのへんで。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
ではでは。
ではなく……もうちょっとだけ続けましょう。
『やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし』ってどんなお酒?
大仙市の秋田清酒には『刈穂蔵』と『出羽鶴蔵』があり、『やまとしずく』は『出羽鶴蔵』がつくるブランドです。
販売は、特約店のみ。
一部の地酒屋さんでしか展開していない、小仕込みのシリーズとなります。
そんな『やまとしずく』ですが、『ひやおろし』の発売は9月上旬ころ。
春にしぼった純米吟醸を火入れして、低温で秋まで寝かせた『生詰め』です。
酒米には『秋田酒こまち』が使われていて、精米歩合は55%……と、ちょっと待ってください。
さっき急に専門用語が出てきましたよね。
「生詰め?」
となりませんでしたか?
日本酒に詳しい方ですら『生詰め』と『生貯蔵』で困惑することが多々ありますし、ちょっと解説をがんばってみます。
『生詰め』とは、火入れをしてから貯蔵したお酒のことを言います。
火入れをすると酵素の働きがとまるので、酒質が劣化しづらい状態で保管することができます。
また、日本酒の大敵である『火落ち菌』。
これを殺菌する役割も果たすので、『生詰め』には『劣化』を防ぐおおきな利があるんです。
『生貯蔵』はその逆をいきます。
生酒の状態で貯蔵して、出荷する直前に火入れをする手法です。
生酒は時間が経つにつれてどんどん甘くなっていくので、貯蔵している間にも味が変化していきます。
火落ち菌がいれば貯蔵している間もどんどん劣化していくので、保管はかなりシビア。
秋田では『高清水』や『太平山』『爛漫』など、王手以外で見かけることは少なくなりました。
いったいどちらが優れているのか。
それは素人である私には判断できません。
ですが、これだけは言えます。
今の主流は『生詰め』です。
瓶詰めしてすぐに湯煎、急冷する『瓶燗火入れ』の後、低温で貯蔵するのが今のトレンド。
あの『十四代』でも採用されていて、一日にできる量は少なくなりますが味は折り紙付きです。
火入れなのにフレッシュ!
そんなお酒に出会ったら、『瓶燗火入れの生詰め』を疑ってみてくださいね。
『やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし』を飲んでみて
この1本の味わいを一言であらわすのならこうなります。
“ひやおろしだけど、ひやおろしじゃないわーーー!”
もうね、とにかく質感がやわらかいです。
すぐに『秋田酒こまち』だとわかる“ふわふわ感”に、やや残り方のある甘み。
この甘み、透明感があります。
そして上品ながらも少しだけ味が乗り、「私、夏酒とはちがうんで」という顔をするんです。
夏酒にはないひとくちの余韻がもうたまりません。
誰が言い始めたのか、やまとしずくにハズレなし。
もしかしたら私なのかもしれませんが、起源などどうでもいいでしょう。
言いたいのはこれだけです。
ハズレなし、まさに。
秋酒にはちがいありませんが、晩秋ではなく今、この瞬間。
残暑のきびしい今だからこそ飲んでほしい1本です。
合わせるのなら秋の味覚にはこだわらず、あなたが今この瞬間に食べたいものと合わせてみてください。
食べたいものと、飲みたいもので。
まだまだきびしい暑さを乗り切ってくださいね。
『やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし』の商品情報
- 使用米:秋田酒こまち100%
- 精米歩合:55%
- アルコール分:16度
- 日本酒度:+0.6(2025年)
- 酸度:1.7(2025年)
まとめ:ひやおろしだけど軽快。まだ夏やん、そんなあなたに
もうね、正直な話、『やまとしずく』というだけで心が躍ります。心が震えます。
涎すら出てくるのでパブロフの犬です。
辛口好きな方にはあまりオススメしませんが、そうでない方にはとにかく飲んでほしい。
秋田酒こまちの甘みは、秋田の甘み。
この甘みがたまらんのです。
軽快な夏酒からの移り変わりを、ぜひ『やまとしずく』で感じてみてくださいね。
それでは今回はこのへんで。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
ではでは。
※おすすめの秋酒を紹介しているので、お手すきの際にでも読んでみてね。